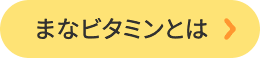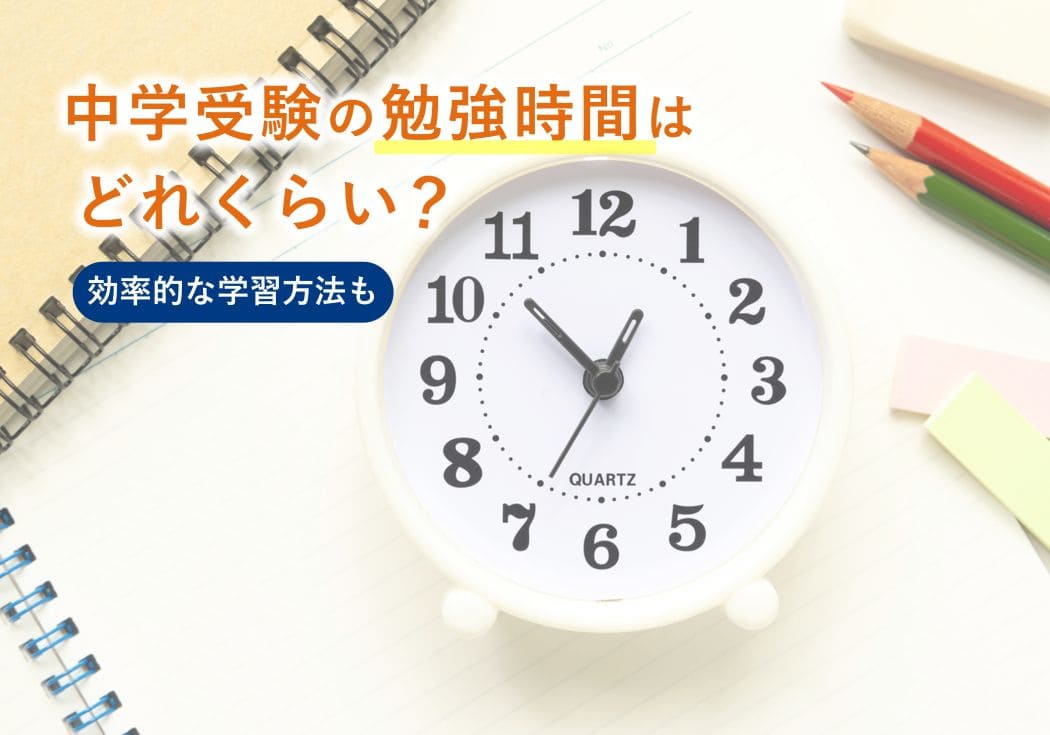大学入試過去問題集を出版している会社は他にもいくつかありますが、全国の幅広い大学の入試過去問題集を出版しているのが、株式会社 世界思想社教学社の「大学入試シリーズ(通称 赤本)」です。大学受験といえば「赤本」というイメージを持ちながらも、「赤本は使うメリットは?」「赤本はどう使うのが正解?」と思っている人も多いはず。
今回は、赤本の基本的な使い方からさらに効果的に活用する方法まで詳しくご紹介します。赤本の活用法についてマスターして、志望大学合格へ一歩近づきましょう。
目次
赤本とは?

赤本とは、正式名称「大学入試シリーズ」と言い、全国都道府県の国公立大学や私立大学および大学入学共通テストの入試過去問題集のことです。本の表紙が赤いことから、「赤本」と呼ばれています。
赤本には、入試本番で出題された過去問が、(通常)3~5年分掲載されています。詳細な解答・解説が付いているため、解いた後に丁寧に採点することで、効率的に理解を深めることができるでしょう。
「傾向と対策」という、大学の出題傾向やおすすめの対策法も載っており、大学合格に向けての必須アイテムとも言える問題集です。
赤本は使用目的によって、利用する時期や方法が異なる!
赤本の利用には以下の3つの目的があり、使用目的によって解く時期が異なります。
➀志望校の入試問題の出題傾向を知る目的
➁志望校の入試問題が解ける学力をつける目的
➂志望校の入試問題で合格点をとる力をつける目的
それぞれの目的について見ていきましょう。
①1年分解いてみて「傾向と対策」から志望大学の出題傾向をつかむ
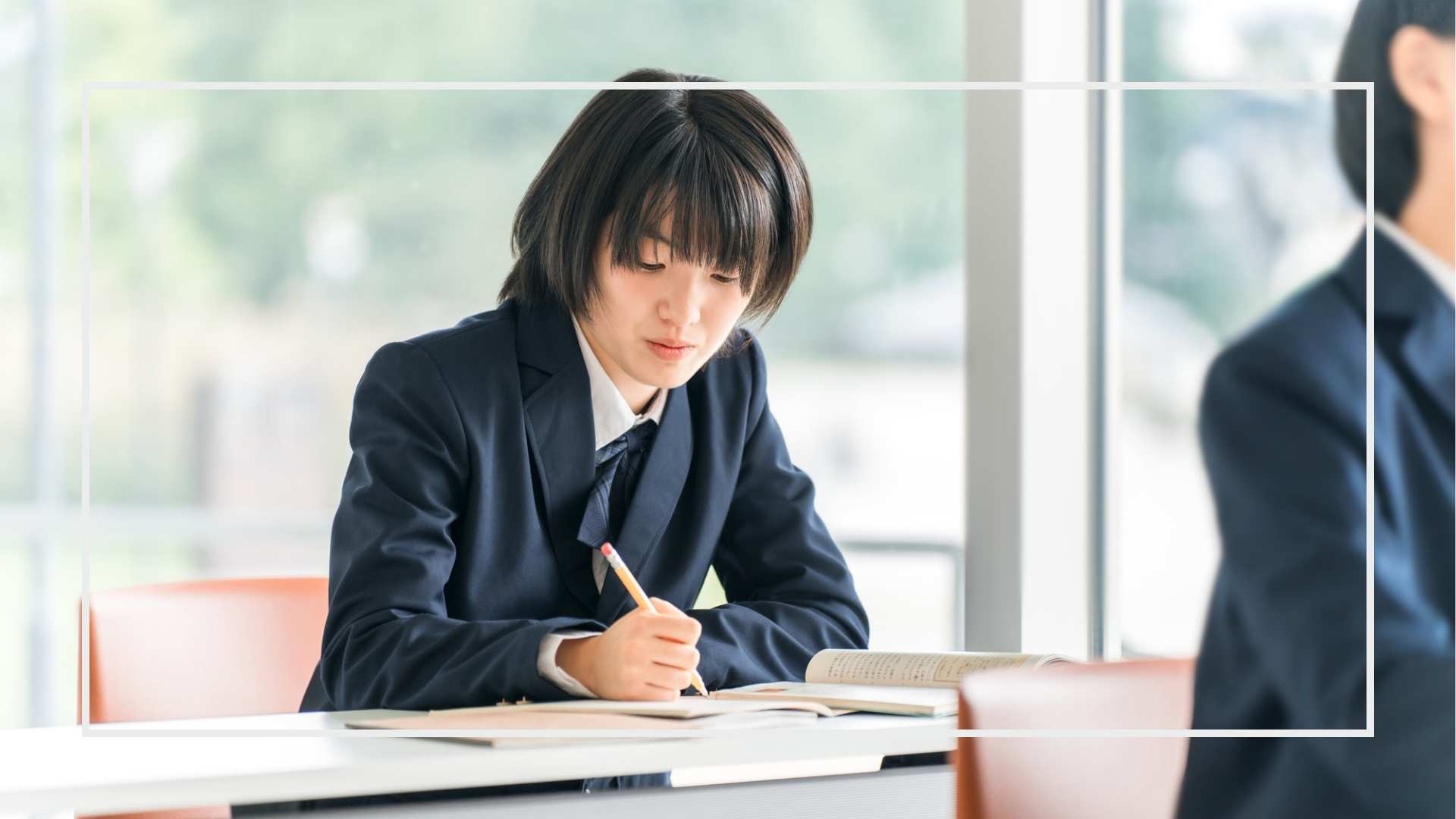
過去問は、一般的に古い年度から最近の年度に近づいていくように解くのがセオリーです。なぜなら、新しい年度から解き始めてしまうと、現在の出題傾向からどんどん遠ざかってしまうからです。
しかし、➀の入試問題の出題傾向を知る目的であれば、志望校を決めたら最新の過去問題を1度解いてみましょう。まだ、出題範囲の学習が終わっていない段階でも構いません。これは、どんな問題が、どの位の分量出題されるのかといった出題傾向を把握するためです。
最新の過去問を解いてみるのは、最新の出題傾向を把握するためです。「最新の過去問を解くのはもったいない」、「最後の総仕上げのために解かずに残しておきたい」と考える人もいますが、昨年と全く同じ問題は、ほぼ出題されることはありません。
解いてみることで、
「生物では遺伝の問題が出るんだな」
「数学はベクトルの問題がなかったな」
「200語程度の英作文が出るんだな」
「日本史は資料問題が多く出るんだな」
「問題量が制限時間に対して多いから、テンポよく解かないとな」
など、特徴がつかめます。
こうして、出題形式や問題の難易度、頻出分野などがわかると、
- どの単元・分野を重点的に学習すべきか
- どの程度の難易度の問題まで対応できるようになる必要があるのか
がわかるでしょう。
赤本には「傾向と対策」という、試験の傾向分析とおすすめの対策法が載っています。「傾向と対策」のページを読むことで、出題形式や問題の難易度、頻出分野などが確認可能です。実際に解いてわかったことと、「傾向と対策」ページの内容を知っておくと、日頃の勉強の優先順位を付けながら効率よく受験対策ができます。
たとえば、英語の「対策例」を挙げてみると、
- 語彙力や文法力・語法力を養成するにはどうしたらよいか
- 会話文や読解問題の傾向や難易度
- どのような時間配分でどのような対策をしておけばよいか
などが記載されています。
②学力アップ目的の赤本利用は基本的に3年生の夏以降に解き始めるのがおすすめ!

➁の入試問題が解ける学力をつけるために赤本を解き始めるのは、(大学の難易度にもよりますが)3年生の夏休み中~9月以降が標準的です。
なぜかと言うと
- 基礎学力が固まっていない早い時期に取り組むと、問題に全く歯が立たず、自信喪失やモチベーション低下につながる
- 基礎に戻って復習しなければならない時間が膨大になって、過去問演習が進まなくなる
といった、非効率な過去問演習になる可能性があるからです。
そのため、まずは夏休み中までに教科書や標準問題集、その大学の過去問を解くうえで基礎レベルとされる問題集で幅広く基礎学力を固め、ある程度土台ができてくる夏休み中~9月以降に、赤本で過去問演習を開始するのがおすすめです。
夏休み中~9月頃に赤本を活用し、➁の学力をつける段階での過去問演習では、問題を解けるようになることが目的なので
- 一旦目安時間を決めて大問ごとに解いてみる
- 目安時間を過ぎたら一旦解くのをやめて、今度は時間無制限で解いてみる
という手順で解いてみましょう。時間無制限ならば解けるのであれば、解くスピードに課題があるとわかるので、解く速さを意識した学習が必要になります。
時間無制限でも解けない場合は、基礎学力が定着していなかったり、基礎事項を使いこなせていなかったりしていると考えられるので、基礎事項に戻って確認しましょう。
たとえば、三角関数の問題が時間無制限でも解けなかった場合は、三角関数の基本を確認してから、過去問を解きなおしてみると良いでしょう。他の年度の三角関数の問題を解いてみて、正解できるかどうか試してみるのもおすすめです。
③解けるだけではなく、得点力を高めよう!

最後に➂合格点をとる力をつける目的です。入試では、制限時間内に、正しい答えを指定された解答欄にどれだけ記入できたかどうかで得点が決まり、合格者と不合格者が決まります。
難関国公立大学の大学入学共通テストは別ですが、満点を目指さなければならない入試問題を出題する大学はほとんどありません。ですから、自分の解けそうな問題を確実に正解して、得点を積み上げていく練習が必要です。
➂の目的で赤本を使う場合は、必ず時間を計り、時間配分や解く順番を意識して1年分を通して解きましょう。マークシート方式の入試を行う大学の過去問は、実際にマークシートに解答をマークして練習しましょう。
マークシートのマークの仕方は、大学ごとに違いがあります。マークミスの原因の多くは、時間不足からくる焦りなので、マークミスをしないよう練習して慣れておくことが大切です。この➂の目的では、合格最低点+αが取れるようになるまで練習しましょう。そうすることで、自信を持って入試本番に挑むことができます。
【Q&A】赤本をもっと効果的に活用する方法

次に、大学合格に向けた効果的な活用方法を【Q&A】方式でご紹介します。
Q1.過去何年分解けばよい?
受験勉強の時間は有限です。志望度合いよって、解く分量は調整して問題ありません。たとえば、本命校であれば10年分が目安になります。併願校についても5年程度は解いておくとよいでしょう。
「安全校」であっても、まったく過去問を解かないのはおすすめしません。なぜなら、過去問を解いておくことで出題傾向や難易度が理解でき、本番でも落ち着いて試験が受けられるからです。まずは1年分を通しで解き、合格最低点以上を目指しましょう。受験までに、3年分程度解ければ安心です。
Q2.たくさん過去問を解きたいときはどうしたらいい?
赤本の収録年数は、大学によって異なります。最新の赤本では、10年前の過去問が載っていないということもあるため、古い年度の過去問が解きたいときは、中古のものを購入するのもひとつの手段です。
ただし、注意点が2点あります。
【1点目】
特に地理や政治・経済では、統計数値が古い年度と現在では異なっていることがあります。「赤本」の正解が、現在では「不正解」となることがあるので注意しましょう。
【2点目】
2025年度より、入試問題は新学習指導要領に沿った出題となったため、過去に頻出だった単元・項目が出題対象外になったり、新しく出題対象となった単元・項目があったりする科目があります。赤本を解く大学の入試要項を、大学のホームページで確認しておきましょう。
Q3解いた後はどうすれば学力アップにつながる?
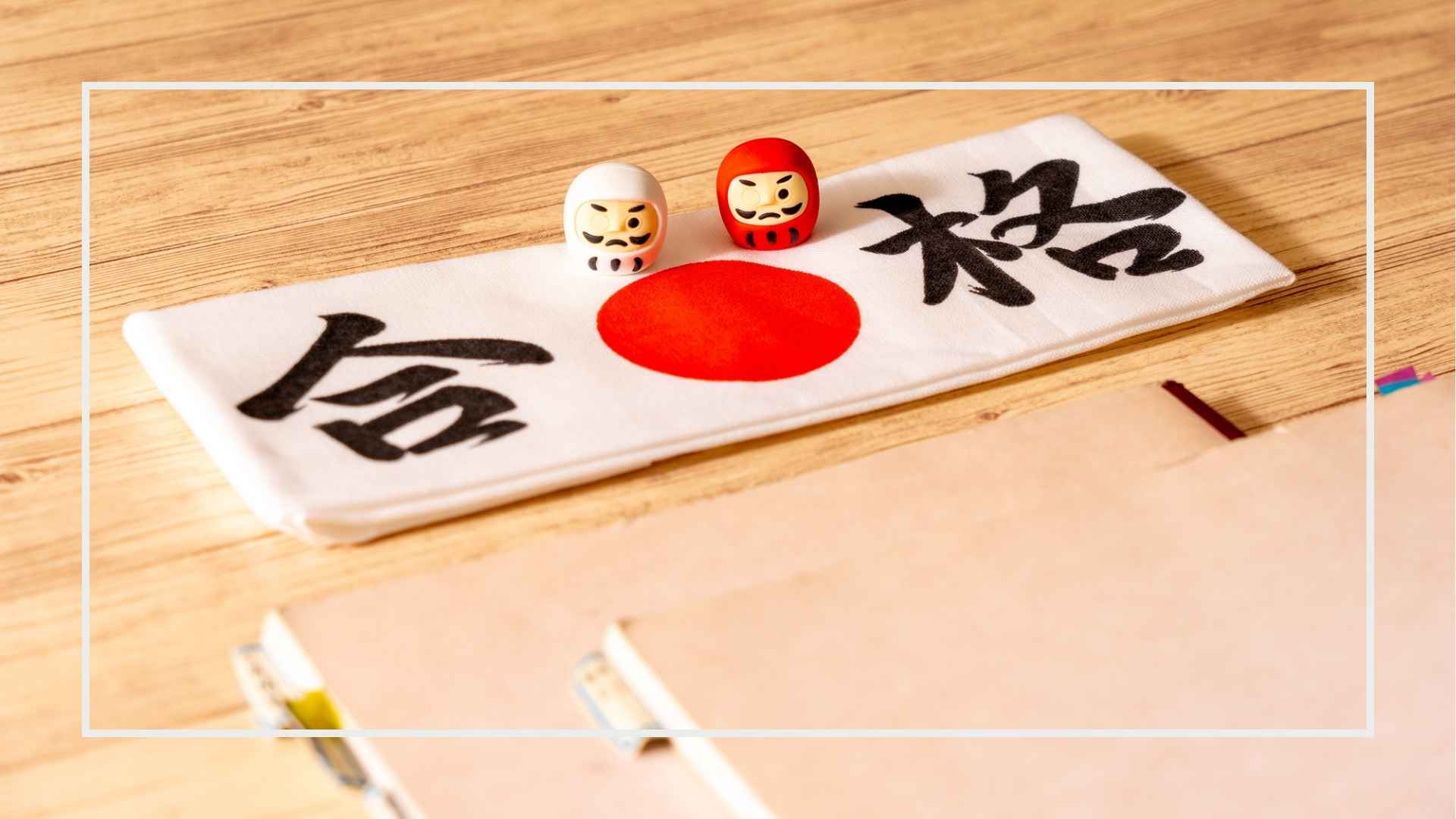
赤本は解くだけで終わらせず、丁寧に採点し、違えたところは解説をよく読むことで、理解が深まります。間違えた問題の原因やどこで間違えたのかを分析したり、効率的に解ける別解があるのかを確認したりしましょう。
一度解いた過去問は、期間を空けてもう一度解き直すのがおすすめです。解き直しは、理解度の定着確認や解答スピードの向上、さらに点数がアップしていれば自信にもつながります。同じ過去問を2~3回解き直すことで、学習効果が高まるでしょう。
初回からの期間が短いと、答えそのものを覚えてしまっているかもしれません。しかし解き直しで確認するのは、「解答へのプロセスを理解しているか」「適切な解法で根拠をもって答えを出せているのか」が大切だということを、ぜひ覚えておいてください。
Q4.「安全校」「実力相応校」「挑戦校」それぞれの赤本活用 の順番は?
志望大学は、合格率80%以上の「安全校」、合格率60~80%の「実力相応校」、合格率60%未満の「挑戦校」の3種類に分けて決定する方も多いでしょう。
その場合の過去問の取り組み方は、合格可能性の高い「安全校」から取り組むのがおすすめです。一般的には、「安全校」の方が問題の難易度が低いため、先に取り組むことで基礎事項の確認ができ、アウトプット力もつけやすいというメリットがあります。
まずは安全校の合格最低点(非公表の場合には7割以上)を達成し、自信が付いたら実力相応校→挑戦校の順に、より上位のレベルの大学の過去問へ移行するとよいでしょう。
赤本で効率的に志望大学合格へ近づこう

大学入試の過去問題集「赤本」は、志望校合格に欠かせない必須アイテムです。最新の傾向把握から学力強化、得点力アップまで目的に応じて使い分けることで、効率的・効果的な受験対策が可能です。赤本を効果的に活用しながら、志望大学合格へ向けて効率よく学習して。「受験対策に不安がある」「過去問演習が難しい」という場合は、個別指導塾を利用してみるのもひとつの手です。
東京個別指導学院・関西個別指導学院では、さまざまな大学の最新情報をいち早くキャッチし、出題傾向も把握しているので、志望校合格に向けて効率よく学習を進めることが可能です。また、大学受験の指導実績も豊富ですので、お子さま一人ひとりに寄り添った学習・受験のサポートが可能です。「大学に現役合格したい」「効率よく受験対策を進めたい」という
【参考】
教学社「赤本入門」 https://akahon.net/akahon60/beginner/

一人ひとりに合わせた学習プランで合格を勝ち取ろう!
東京個別指導学院・関西個別指導学院では、生徒一人ひとりの学習状況と目的・目標に合わせた、学習プランの作成により合格率を高めています。全国の大学の入試制度や出題傾向など、進路指導に必要な最新情報を幅広くキャッチしているため、効率のよい受験戦略についてもご相談可能です。ぜひ以下より詳細をチェックしてみてください。