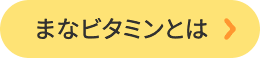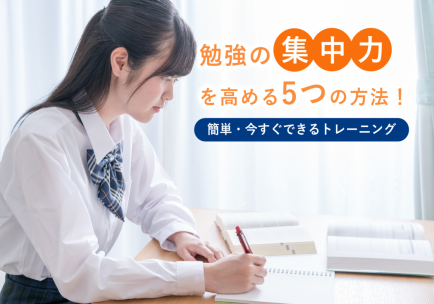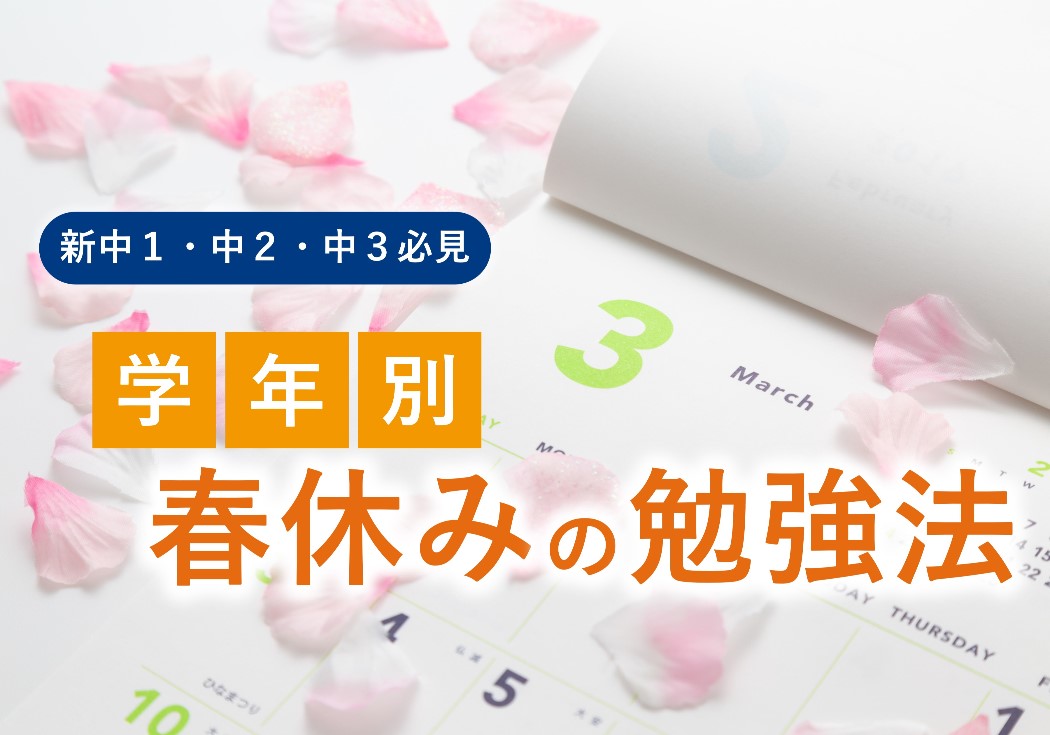「志望校合格に向けて勉強しなければいけないのに、集中力が続かない…」
「いざ勉強を始めても3日坊主で継続ができない…」
このような悩みを抱えている受験生も多いのではないでしょうか。
今回はそんな勉強がなかなか続けられなかったり、苦手意識のあったりする方のために「正しい勉強を続けられる習慣・環境づくり」について総フォロワー数が20万人以上の学習インフルエンサーのいゆぴさんに、お話を伺いました。
勉強が苦手で偏差値が45だった状況から1年間で65まで上げることができたご自身の経験を元に、勉強習慣を5つご紹介いただいています。
ぜひ自分の勉強習慣を見直す機会にしてみてください。
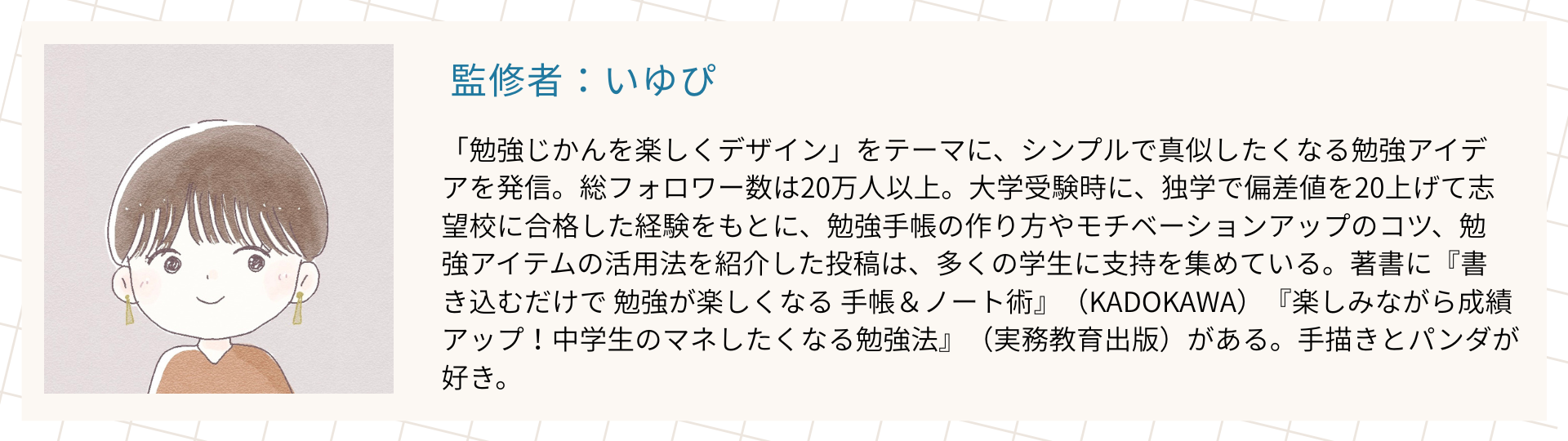
今回私が1年間で偏差値を45から65に伸ばしたときに、実際にやっていたことを5つご紹介したいと思います。
元々勉強に苦手意識を持っていて、受験勉強を始めるタイミングでは偏差値が45ほどでした。そこから志望校合格を目標に、自分なりの方法で勉強をし始めて1年間で65まで上げることができました。
やってみて思ったのは、「ガムシャラに努力するよりも、正しい方向で継続することが大事」だということです。
今回は、勉強法や使った教材の話ではなく、「勉強に取り組むための習慣・環境」についてまとめました。テクニックだけではない、土台を整えることで、成績は変わるものだと考えています。
目次
1. 睡眠時間は削らない
成績を上げたいという思いが強いと、「少しでも長く勉強時間を確保しなきゃ」と考えて、つい夜遅くまで机に向かってしまいがちです。
私も最初はそうでした。睡眠時間を削って勉強するのが努力の証のような気がして、夜更かしを繰り返していた時期がありました。
でも、あるとき「眠いまま勉強しても、内容が頭に入らない」ことに気づいたんです。復習してもやったところが定着しておらず、「あれ?これ、昨日やったはずなのに……」ということが何度も起きて、「睡眠を削るのは逆効果」なのではと考え直しました。
それからは睡眠を大事にするようになり、毎日7~8時間の睡眠を確保するようにしました。すると勉強に集中できるようになり、結果的に一気に勉強効率が良くなった気がします。
そのため、受験生の時は23:00就寝〜朝6:00起床という生活リズムを意識して、睡眠時間をキープするようにしました。
寝ている間に記憶は整理・定着されると言われています。勉強した内容をしっかり身につけるためにも、睡眠は欠かせない要素の1つと私は考えています。
もちろん、毎日理想通りに眠れるとは限りません。それでもできるだけ、「最低でも6時間以上は寝る」「寝る直前にスマホを見ない」「毎日同じ時間に寝る」など、自分に合った方法で睡眠時間を確保するようにしてみてくださいね。
「たくさん勉強したはずなのに成績が伸びない……」と感じている場合は、睡眠時間を見直してみると、突破口になるかもしれません。
2. Todoリストを書く

「さあ勉強しよう!」と思って机に向かっても、
「…で、今日は何をやるんだっけ?」と、最初の一歩で止まってしまうことってありませんか?
私も手当たり次第に参考書を開いたり、思いついたことから手をつけたりしていたんですが、どうも集中しきれず、時間だけが過ぎていく感覚に焦りを感じていました。
そんなときに取り入れたのが、毎日の「Todoリスト」を手帳に書くことです。
これがすごく効果的で、勉強を始める前に「何をしようかな…」と悩む時間が減り、メリハリをつけて勉強できるようになりました。
今日やるべきことが可視化されることで、「何をやるか」を悩む時間が激減。自然と優先順位もつけられるようになりました。
終わった項目にチェックを入れると、自然と達成感も得られます。
「今日もちゃんとできた!」という小さな成功体験が積み重なり、自信も持てるようになりますし、モチベーション維持にも効果的です。
オススメは学校での帰りのホームルームの時間に「今日やること」を書き出しておくこと。そうすると、TODOリストを書き出す時間を節約できます。
もう一つは、勉強を始める直前に、その日のやる分を決めてから勉強を始める、というやり方もおすすめです。
指針がないまま勉強をするよりも、迷わずに勉強を進められるので、TODOリストを作る時間を確保したとしても、その方が勉強の質は向上すると考えています。
TODOリストを作るコツは、やることを詳しく書くこと。例えば、「英語の復習」ではなく、「英語の問題集p23-24」のように、項目を見ただけで何をすればいいかを、ひとめで分かるように書きましょう。
そうすることで、勉強する時になにをすればいいか迷うことがなくなります。
3.放課後は勉強場所に移動する

学校から帰宅すると、どうしても気が緩んでしまいませんか?
「ちょっと休憩のつもりが、いつの間にかスマホを触って1時間経ってた…」という経験、きっと誰にでもあると思います。
私自身も、家に帰ると一気に気が抜けてしまって、勉強モードに切り替えるのが難しかったので、「勉強は家以外の場所でやる」と決めました。
具体的には、放課後そのまま学校に残ったり、近所の図書館に移動したりして勉強をすることにしたんです。
「静かにするのが当たり前な場所」や「人の目がある場所」だと、適度な緊張感があって自然と集中モードに入りやすくなります。
家ではいまいち集中しづらい、勉強モードに入りづらいという場合は、カフェや公共のスペース、学校や塾の自習スペースなど、自分が集中しやすい場所を見つけてみてはいかがでしょうか。
「ここに来たら勉強する」と自分の中で決められる環境を持つと、勉強モードへの切り替えがスムーズにできるようになります。
4. 勉強のスタート時間を決める

受験勉強を始めたころ、私は「平日は5時間!休日は10時間!」と意気込んで、毎日の勉強時間に目標を立てていました。
でも、部活や体調、気分の波もある中でその時間を毎日達成するのは正直きついこともあります。
できない日が続くと、自己嫌悪でやる気も落ちてしまう…そんな悪循環に陥ることもありました。
こういった経験をお持ちの方も、多いのではないでしょうか。
そんなときおすすめなのは、「何時間やるか」を目標にするのではなく、「勉強のスタート時間を決める」ことです。
例えば、平日は帰宅後に夕食を食べた後の19時〜、休日は午前は9時〜、午後は13時〜 など「勉強のスタート時間」だけを固定します。
時間は多少前後したとしても、「この時間になったら、机に向かう(勉強をスタートする)」とルールを作ることで、自然と勉強スイッチが入るようになりました。
何かを始めるまでが一番エネルギーを使うので、ルーティンとして行動のきっかけを作っておくと、迷いなく動けて、目標を達成しやすくなります。
「夜に勉強しよう」など、ざっくりとした時間帯が決まっている人は多いと思いますが
「19時から始める」など、具体的な勉強の開始時間を含めた勉強ルーティンを決めることで、より習慣化しやすいです。
もう一つは勉強以外のルーティンを決めること。
起床時間、就寝時間の2つを決めておくと生活のリズムが生まれ、毎日の勉強ルーティンを継続しやすくなります。
5.わからないことを放置しない
分からない問題を後回しにしてそのまま放置してしまった経験、ありませんか?
解答を見ても理解ができず腑に落ちないときってありますよね。
そんなときは学校の先生や塾の先生、周りの大人に質問、相談をしてみてください。
わからないことを放置して勉強していると無駄な努力になってしまっていることもあります。
何が分からないかも含めてアウトプットすることで理解がさらに深まります。
私の周りには相談しやすい先生など勉強を続けやすい環境があったので、独学で勉強をしていましたが、気軽に質問しやすい大人が周りにいなかったり、今の自分の勉強が合っているのか不安になったりしてしまう方は個別指導塾などの塾に通うことも1つの選択肢だと思います。
自分に合った勉強環境を作るなら

たとえば、ベネッセグループの東京個別指導学院・関西個別指導学院のような個別指導塾では、1人ひとりに合わせて学習計画や勉強法を提案してもらえるので、「今の自分に合った勉強法」が見つかります。
また、相性のよい先生を自分で選べる(※1)ので、質問しやすく、わからないままにしない学習環境も整っているのが心強いポイント。無料の自習スペースでは、手の空いている先生に質問できる(※2)など、その場でわからないを解決できる環境なので、苦手が詰み上がる心配がありません。
「今の勉強法に自信がない」「気軽に相談しやすい大人が周りにいない」そんなときは、まずは無料の体験授業や教室見学に足を運んでみるのもおすすめです。
東京個別指導学院・関西個別指導学院の
無料体験・教室見学はこちらから
※1教室状況によって、担当講師をご相談させていただく場合もございます。
※2自習スペースは、教室によって使用状況(条件)や有無が異なる場合がございます。
最後に

自分に合った勉強法を取り入れることは大切。でも、どんな良い方法も「続けられなければ」結果につながりません。だからこそ、「継続できる環境づくり」が大切だと考えています。
自分が無理なく続けられるスタイルを見つけ、相談できる環境を整えることが成績アップの土台になると私は感じています。
手っ取り早く偏差値を上げたいがために具体的なテクニックばかりに目を向ける方もいらっしゃるかもしれませんが、正しい方向にコツコツと進むことで、私は偏差値を上げることができたと感じています。
まずは「勉強を継続できる環境づくり」をしてみてはいかがでしょうか?